はじめに(独自見解の明示)
本記事は筆者(シマYi)の独自の感想・解釈です。私が実際に視聴・読了した範囲での共通点をまとめたもので、公式見解や絶対評価ではありません。
作品によって例外は多々ありますが、「負けイベント(=物語上、味方が意図的に敗北する局面)」に通底する“匂い”を3パターンで整理します。
冒頭:なぜ“負けイベ”は燃えるのか
強敵にぶつかって一度は敗れる——いわゆる“負けイベ”は、主人公側の限界提示と世界のスケール拡張を一気に伝える装置です。
あるある①:元敵が味方入り→さらに上位存在の噛ませに
敵だった実力者が合流すると、往々にしてその直後に“さらに上”が現れ、戦力差の見本市になります。
・例
進撃の巨人
女型の巨人(アニ)や鎧の巨人(ライナー)が味方サイドと歩調を合わせた局面で、エレン崇拝の人間側から雷槍に翻弄されぼこぼこにされる。
グラップラー刃牙
一時は敵対関係の花山やガイアが味方になった瞬間、範馬勇次郎という作中最上位が“格の違い”を見せつけます。味方化=即戦力のはずが、“上には上がいる”演出の踏み台にされがち。
あるある②:「ゾクッ…」の威圧と共に新敵登場
初見の圧、未知の能力、名も明かさぬまま漂う殺気。こうした登場演出が挟まると初戦は負けの確率が跳ね上がる印象です。
・例
七つの大罪
十戒のガラン初登場時、メリオダスたちはなすすべなく蹂躙され、敗北した様子が伺えます。
HUNTER×HUNTER
キルア&ゴンが初めてネフェルピトーと対峙した瞬間、圧倒的強者の殺気=死が一気に整う。登場“直後”は勝てないという思いが生まれました。
あるある③:心の声が味方に偏る時は危険信号
戦闘中のモノローグが味方側にだけ濃い回は、しばしば思考が“詰み筋”の確認になっています。
・例
呪術廻戦
五条(学生)vs甚爾では、五条が相手の手の内を探る心声が重なった末に敗北を喫する局面が印象的(甚爾側の心声は最後の止め時のみ)。
ドラゴンボール超
スーパードラゴンボールをめぐる戦いにて、ベジータvsヒットでも、ベジータの分析が多く描かれ、ヒットは無言で詰めてくる。語るほどに追い込まれている。
まとめ(私見)
ここで挙げたのは、あくまで筆者が見た範囲の“体感則”。実際には勝ちイベでぶち抜く作品も多く、作品ごとの文法差も大きいです。それでも、
- 元敵の味方化直後は“上位の壁”を見せる噛ませになりがち
- 威圧演出での新敵登場は初戦敗北のサイン
- モノローグ偏重は追い詰められている暗号
この3点を頭の片隅に置いておくと、次話の展開読みや考察の軸が作りやすくなります。
※コメントの際は日本語でお願いいたします。


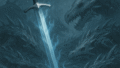
コメントを残す コメントをキャンセル